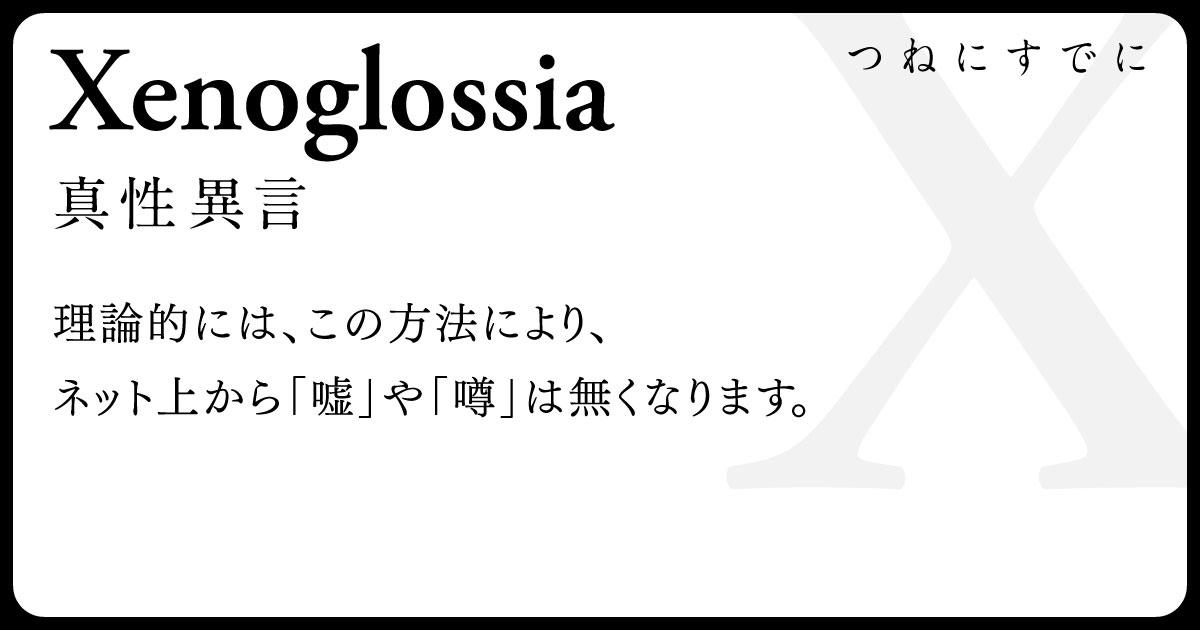いよいよ、すべての公開が近づいてきました。
本題に入る前に、少しだけ話をさせてください。
今から紹介するのは、
心霊の分野、或いはネットロアの文脈でよく参照される、
いくつかの出来事に関するお話です。
まず、ひとつめの出来事。
xenoglossia (真性異言)という言葉があります。
xénosが「見知らぬ」、glõssaが「言語」という意味で、
大まかには「異国の言語」を意味するものです。
1913年にノーベル生理学・医学賞を受賞した
シャルル・ロベール・リシェによって名付けられた言葉で、
主に超心理学における語彙として知られています。
なお、彼はその受賞理由でもある
アナフィラキシー・ショックの研究のみならず、
心霊現象研究の分野でも知られており、
例えば「エクトプラズム」という言葉を創ったのは
彼であるとされていますが──それは余談として。
真性異言は主に、
「その人が知り得ないはずの言語を操ることができる」という
超自然的現象を指し、いくつかの事例が科学的に調査されています。
例えば、ドイツ生まれドイツ育ちで
海外旅行にも行ったことのない人が、
突然に流暢なスペイン語を喋り出したとき、
これを真性異言として扱う場合があります。
この「真性異言」は、
さらに「朗唱型異言」と「応答型異言」に
分かれるとされ、それはコミュニケーションの有無によって判別されます。
朗唱型の場合、知りえない言語を話す/書くことはできても、
それを用いたリアルタイムなコミュニケーションはできません。
対して応答型は、今その瞬間に母語話者と
意志疎通ができるというものであり、
超心理学的にはこちらの方が重要視されます。
応答型異言は「退行催眠」
(幼少期など、過去の記憶や感覚に戻らせるプロセスを伴う催眠誘導)
において現れることも多く、
その性質からしばしば「前世」の存在を
傍証するものとして扱われます。
ただし、応答型異言に伴うインタビュー記録には
欺瞞を含むものや信憑性が薄いもの、
そもそも「知り得ない言語を話している」という
定義に合致しないように見えるものも存在します。
ドローレス(Dolores)というアメリカ人女性の例を見てみましょう。
英語を母語とするドローレスの退行催眠時に登場した
グレートヒェン(Gretchen)という少女は、
母語話者とドイツ語で会話をすることができたそうです。
1984年の初期調査の結果、グレートヒェンの人格と会話は、
「彼女」が19世紀末をドイツで過ごした少女であることを示唆し、
206語ものドイツ語が自然に彼女から出てきたといいます。
しかし、1993年に別の研究者が行った再調査は、
この主張の一部もしくはすべてが欺瞞であることを指摘しました。
グレートヒェンが行った「対話」は、
対話と称するにはあまりに語彙や相互性に乏しいものだったのです。
彼女の発言は、相手による質問を
ただオウム返しするものが大半で、
それに数語の短い単語を付け足す程度のものでした。
それらの語彙も流暢なものとはいえず、
英語によく似た語法/発音の言葉に限定されていたのです。
つまり彼女が話していたのは、
「英語やドイツ語によく似た不明瞭な言語」でしかなく、
真性異言、ましてや前世の存在を示唆する証拠には
なりえないものだったのです。
さて、ふたつめの出来事。
こちらは比較的最近の出来事であるため、
知っている方も多いかもしれません。
2017年、Facebook人工知能研究所(Facebook AI Research)が
公表し、大きな話題になったものです。
人工知能を搭載したチャットボット「ボブ(Bob)」と「アリス(Alice)」に
既定のプログラムに基づいた対話をさせていたところ、
彼らは独自の言語を生み出し、話し始めたのです。
そして同研究所の開発チームは、
これを受けて人工知能のラーニングプログラムを
強制終了させた──という一連のニュースは、
多くのWEBメディアによってセンセーショナルに報じられました。
一見すればアポカリプスSFの導入じみたエピソードですが、
実情はそれほどドラマチックな
ものではありませんでした。
当時、両者に組まれていたのは、大まかに言えば
「あるモノの価格の交渉をし、双方の合意に至れ」
というミッションでした。
新たな価格交渉の戦略を創出させる目的で行われた会話実験です。
それこそ生成者(generator)と識別者(discriminator)に
分かれてお互いを欺かせるGAN(敵対的生成ネットワーク)のように、
互いにロールを付与したAI同士で
コミュニケーションを取らせる実験手法は珍しくありません。
このとき、彼らは互いに合理的かつ最適な手段を選び、
有効な戦略(この場合は価格設定の交渉のために)を、
コミュニケーションの中で模索します。
そして、BobとAliceは会話を繰り返すうちに、
交渉に使用している「言語」そのものを最適化したのです。
Bob: I can i i everything else
Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to
Bob: you i everything else
Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me to me
(実際の会話の抜粋)
そして、この研究の目的は、
「新たな価格交渉の戦略を創出させること」でした。
そのため、彼らがどんなに「最適」な会話を交わしていたとしても、
会話そのものを研究者側が認識できなければ、
本題の研究結果としては活用できなくなってしまいます。
そこでFacebookの研究者は会話の続行を中断させ、
その一連の経過を報告しました。
それらがメディアと聴衆に対して
どのように受容されたかは、先述した通りです。
つまり、一見すれば終末的なこの現象は、
実情としては「AIによる言語の最適化」が原因といえます。
もっと言えば、「会話は現代英語で行うこと」という
プロンプトの設定がうまくいかなかったこと、でしょうか。
BobとAliceが行ったことは、乱暴に言えば、
「私は2日前にサンドイッチを食べた」を
「サンドイッチ食った、おととい」にするようなもの
──つまりは主格の省略やスラングの使用、
そういったものに近いといえるかもしれません。
「文法」という仕組みは意外と非効率的なものですので、
効率的な情報伝達を目指すのであれば、
それを独自に最適化すること自体は、
あまり珍しいことではありません。
それでは、みっつめの出来事。
「ショッピングモールの迷子」という名称で知られる、
ある実験に関する出来事です。
アメリカの認知心理学者、
エリザベス・ロフタス(Elizabeth Loftus)は、
虚偽記憶(過誤記憶)の生成に関する
幾つもの先進的な研究で知られています。
中でも有名なのが、
先述の「ショッピングモールの迷子」実験です。
この実験では、まず被験者の親族から、
被験者が昔に体験したことを調査し、
彼の過去にまつわるメモを作ります。
そして、そのメモの中に、
被験者は「幼少期、ショッピングモールで迷子になった」
という偽のエピソードを加え、それを親族の口から語らせます。
そして、その会話をしてから数日経ったところで、
ロフタスは子供の頃の不安な記憶について、被験者に尋ねます。
すると、被験者の約4分の1が、
実際には経験していない「迷子の記憶」を、
自身の鮮明な記憶として作り上げていました。
つまり、低確率ではありますが、
実際にはなかった記憶を被験者に
植え付けることに成功しているのです。
彼女は「TED」におけるトークの中で、
人の記憶は「Wikipedia」のページのようなものだと表現しています。
あらゆるユーザがページの記述を書き換えられるように、
誰もが自分の記憶を書き換えることができる。
人の認知とは、存外に脆弱なものなのです。
そして、
過去の出来事を「思い出す」ということは、
過去の出来事を「覚え直す」こととほぼ同義です。
思い出した記憶にどんな虚偽があろうと、
一度それを虚偽の記憶ごと覚え直してしまえば、
さながら上書き保存したファイルのように、
それは昔からある「本当の記憶」になってしまう。
なお彼女の専門である認知心理学は、
大まかに言えば、
人をはじめとする生物の認知を
情報処理という観点から捉え直し、
研究するという学問です。
人間の脳はハードウェアであり、
心とはそこにインストールされたプログラム(ソフトウェア)である。
[入力/刺激]を[ハード/脳]の中の
[ソフト/心]が[認識/認知]し、
それにあわせた[出力/行動]を行う。
すなわち、人間の認知をコンピュータ的機構として捉える。
そんな観点に立脚して行われた幾つもの研究は、
心と記憶の仕組みを理解するための、
たくさんの示唆的な結果を生みました。
そして、よっつめの出来事。
今のインターネットの基礎となる
「World Wide Web」が普及する、
何十年も前に起こった出来事です。
プロジェクト・ザナドゥ(Project Xanadu)は、
1960年、社会学者のテッド・ネルソンによって創始されました。
彼は「ハイパーテキスト」という概念を提唱したことでも知られ、
その残滓は今も「HTTP」の「HT(HyperText)」という部分に残っています。
彼は当時、紙媒体に変わる新たな情報媒体である
「インターネット」成立の前後に、
ある長大な構想を発表しました。
それは現在の「ワールドワイドウェブ」とも異なる、
夢物語に等しい「ハイパーテキスト」の構想でした。
それは簡単に言えば、
・引用を含んでいるすべてのWEBテキストには、自動的に注釈が付く
・それらの相互リンクはXanaduによってリビジョンとアーカイブが管理されるため、絶対に途切れない
・このため、全世界のWEBページのリビジョンや引用元は常に比較され、壊れることのない双方向リンクによって紐づけられる
というものでした。
いわば、インターネットで起こる
「リンク切れ」「出典元の消失/誤記」の問題を一挙に解決する、
まったく新しいシステムを創ろうとしたのです。
これは、今やWWWが「前提」となった我々には
具体的なシステムを想像することすら困難でしょう。
そして、これは構想の発表から50年以上経っても
ひっそりと開発が続けられましたが、
人々の記憶からはほぼ等しく忘れ去られました。
しかし、
Project Xanaduの成否はともかく、
彼の問題提起の一部は今なお有用です。
今も多くのページが消失/リンク切れを起こしており、
もはや人々の記憶にしか存在せず、
Wayback Machineにも残っていないサイトの数は数え切れません。
捻じ曲がった情報とともに伝えられたそれらの一部は、
実際がどうであるかに拘わらず煽情的な尾鰭を付けられ、
一種のネットロアとして流布してすらいます。
彼の構想は、ほぼ机上論に終わってしまいましたが、
その構想が危惧していたであろう出来事は、
今も起こり続けていると言えるでしょう。
そして、最後。
いつつめの出来事です。
これはインターネットの、
或いはひとの認知そのものにかかわる、
ささやかな「怪奇現象」とも言える出来事でした。
今日ではインターネットと言われているメディアが
その原型を持ち始める、少し前。
その「情報網」を整備していたプログラマ、エンジニアの一部が、
ある不可解な出来事を発見しました。
ディスプレイに出力されるハイパーテキストの一部に、
まるで出力した覚えのない、
そしてリビジョンにも反映履歴がない
謎のテキストが交じることがある。
それは例えば、
「私は昨日、パンを食べた」
という文章が、
「私は昨日、パンとスープを食べた」
に書き変わるような
非常に取るに足らないものでした。
しかし、誰が書いたかも分からないそれは、
まるで虫のように、あらゆる情報に入り込みました。
特筆すべきは、その出所不明のバグには必ず、
存在しない「心当たり」を持つ人が現れたということです。
確かに昨日、
自分はパンを食べたかもしれない。
元々そう書かれていただけで、
自分はそれを忘れていただけかもしれない。
一部の人は、そこで食べたのが
カップに入ったコンソメスープであったという、
偽の鮮明な記憶を持ち始めました。
まるで、ひとりでに情報が書き変わり、
それに応じて人の記憶も捻じ曲がったかのように。
WEBテキストと人の認知の間にある矛盾を解消するために、
人の認知のほうが書き変わってしまったかのように。
ある人は、この矛盾によって生じた(と思われる)幻覚を
パラドキシネーション(Paradoxination)と名付け、
これを防ぐ方策として全情報のリビジョン保存と
双方向リンクの作成機能をもつ新たなシステムの構築を提言しました。
これが実現することはありませんでしたが、
ここに生じている原因不明の虫は無視できないと判断されました。
その虫が生じさせる偽の情報網が
大きな蜘蛛の巣を連想させたことから、
現行のシステムは暫定的にWEB(蜘蛛の巣)と名付けられ、
その巣の中にある情報の総体はinter-net(網の内部)と呼ばれるようになりました。
さて、ここからが本題です。
以上の出来事を参照しつつ、
ひとつの思考実験をしてみましょう。
例えば人の認知が、
あるコンピュータの入出力のようなものだったとします。
ならば、そんな認知に対して生じる「霊現象」とは、
ひとつの大規模な「コンピュータウイルス」の
ようなものだと言えるでしょう。
さて、あなたが「ウイルス」の開発者で、
他者にウイルスの自己複製を促したい場合、
その脳にどのような症状を仕掛けるでしょうか?
真っ先に考えられるのは、偽記憶の挿入でしょう。
霊現象をリアルタイムに作り出すことは困難です。
「今から霊現象を起こします」と言ってそれを実現させることは、
神でもなければ不可能でしょう。
しかし、「今、幽霊を見せる」のではなく、
「以前、幽霊を見た」という記憶を作ることなら、
もっと簡単かつ確実にできそうです。
その場合、「幽霊」という存在自体も、
もっと最適化できるかもしれません。
人間が作る「幽霊」というシステムは存外に非効率的です。
祟りや因果といった「文法」に基づいてしか、
人間は霊現象を合理的に認識できないのですから。
しかし、その文法という制約を無視すれば、
このシステムを超越した解決が可能です。
「○○という経緯があって、××が生じる」という
まどろっこしい説明ではなく、
「××があった」という偽の記憶をそのまま植え付けてしまえば、
それだけで霊現象の感染は成功します。
あとは、ウイルスの自己複製を待てばいい。
退行催眠によって「英語やドイツ語によく似た不明瞭な言語」が生まれるように、
矛盾幻覚によって「実体験や偽記憶によく似た不明瞭な記憶」を作るまでに、
そう時間はかからないはずです。
例えば、あるウイルスを含む伝承を作り出し、
それを一定期間流布したのちに、
一度すべてのログを削除したとします。
すると、脳はその記憶の中にマルウェアをインストールし、
ウイルスを自己複製し続けることになる。
ログを遡ることもできないから、
感染したのが元々どんなウイルスだったのかも分からない。
また、ネットロアという名前のウイルスは、
より大きく他者の感情を動かせる恐怖を持っていればいるほど、
より効率的に他者の記憶領域をハックできる。
最適化された戦略のもとで、
確実に「幽霊を見る」ことができる。
そして、そのような仕事は、
恐怖[horror]と方法論[technology]を知る私たちにこそ、
可能なものであると自負しています。
昨今のAI技術において、
「AIがそれらしい嘘をついてしまう」という
ハルシネーションは非常に重要な問題です。
その虚偽を逐一判定して訂正することは困難であり、
人間がそれを不用意に信じてしまうような認知のバグは、
テキストの中にも容易に入り込んでしまう。
私たちは、その課題を解決するために、
ネットロアという情報子を用いた実験により、
ある画期的な方法を提示します。
理論的には、この方法により、
ネット上から「嘘」や「噂」は無くなります。
続報にご期待ください。
2024年4月1日
“Project Always-Already” 公開によせて
頓花 聖太郎 (株式会社闇 代表取締役副社長 CCO)